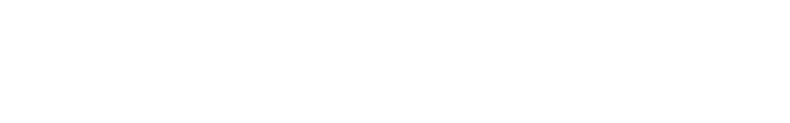僕等の住む世界には、
自分の尺度だけでは
咀嚼できないような
素晴らしいことがある
Interview
ペンギン・ハイウェイ
監督
石田祐康ひろやす
原作は情報量が多く、
全部描き切れるのかという懸念があった

――森見登美彦さんの原作とは、どのように出会ったのでしょうか?
石田:京都の学生時代に様々な出会い方で森見先生の作品はよく読んでいたのですが、この作品は様々な方から強く薦められたことがきっかけです。僕が所属するスタジオコロリドの人たちも、僕が映画化するのに向いていると思っていたようです。ただ、まさか本当にやることになるとは思ってもみませんでした(笑)。
――どのように話が進んでいったのでしょうか?
石田:実はオリジナルや他の原作も含め可能性を検討していたのですが、その中でも『ペンギン・ハイウェイ』に最も惹かれたんです。ただ、同時に(映像化するのは)難しいとも思いました。原作を読むと判るのですが、とても情報量が多い。いろんなことが日記形式で書かれていて、酸いも甘いもあり、さらには奥深なSF要素もある。それを全部描ききれるかどうかという懸念がありました。

――劇団「ヨーロッパ企画」を主宰している上田誠さんが脚本を担当されていますが、森見さんとは『四畳半神話大系』や『夜は短し歩けよ乙女』のアニメ化でも組んでいますよね。
石田:森見さんと上田さんは親交があって、森見さんは上田さんに大きな信頼を置いています。これまでの作品で実績がありますし、物腰がとても柔らかく、明晰に物事を考えておられる方でもある。かつ、森見さんの成分を自分の中に吸収して“森見さん節”を本人に代わって書くことが出来る。他にも多くのことを察してくださる。なので一緒にお仕事をしていてとてもやりやすかったです。
――石田監督は脚本にどの程度関わったのでしょうか?
石田:大枠から台詞の細かい部分まで、考えたことは忌憚なく全部お伝えしました。上田さんは京都にお住まいなのでメールでのやりとりと、定期的に東京に来ていただいて直接打ち合わせもしました。その時、ホワイトボードにユーモア溢れる図式を描きながら、構成の提案をされていたのが印象的でしたね。


ノートの存在は、『四畳半神話大系』の
主人公“わたし”にとっての
“四畳半の部屋”のようなものであるべき

――劇中、主人公のアオヤマ君が研究の詳細を記しているノートが登場します。そこでは“小学生が鉛筆で書いたような記述”によってページがめくられるという難易度の高い作画が成されています。
石田:アオヤマ君にとってノートが重要なアイテムであることははっきり判っていました。もちろん、アニメーションの表現として大変な部類に入ることも判っていました。脚本作業が進むうち、映画では原作の一人称視点によるモノローグを多用できないということがだんだんと判ってきたんですね。なら、それを代弁する形で「ノートを使わずしてどうする」と考えたんです。アオヤマ君が考えることは大体ノートに書かれていくので。もっと踏み込んで自分は、ノートの存在は、『四畳半神話大系』の主人公“私”にとっての“四畳半の部屋”のようなもの、と仮定していました。アオヤマ君が使う方眼用紙も四畳半も美しい正方形ですしね。

――アオヤマ君は“お姉さん”に対する研究もノートに記していますよね。
石田:まず、アオヤマ君の性格だと、方眼用紙のマス目ひとつひとつにかっちりと文字をはめ込んで書いてゆくのが癖ではないかと想像しました。彼にとって世界を測る尺度が、このマス目なんです。『四畳半』の“私”の尺度が四畳半であったように。アオヤマ君は見聞きした事をマス目にはめ込み、分節することで、初めて咀嚼したり吸収したりできる。一方で、理解できない、あるいはこれから経験したり知らなくてはならないような物事もある。そのマス目に収まらないようなものの代表として“お姉さん”という存在があるんです。

――“お姉さん”の部屋でアオヤマ君が彼女の顔を間近で見た時「その感情をうまく描くことができなかった」というくだりがありますよね。
石田:だからアオヤマ君は(自分の世界である)マス目に収めることができないんです。ノートに書いてあるその時の驚きや嬉しさに関しては、あえてマス目の中に収まらないように描いています。よく見ると、いつものアオヤマ君らしからぬ文字の大きさと配列になっているんですよ。
――アオヤマ君の持つ理論的な思考よりも感情が勝ったと。
石田:勝ったからはみ出しちゃったんですね(笑)。そういうアオヤマ君の気持ちを象徴するのがノートなんです。上田さんも明確に「この作品の柱はアオヤマ君がお姉さんに対して抱く恋慕の気持ち」と仰っていました。それを経糸にしながら、クラスメイトのハマモトさんとの三角関係や友情が緯糸になるような図式を、上田さんがホワイトボードに描いて下さったんです。森見さんが重要視したと思えるものは逃さずなるべく拾うようにして、原作の豊穣なエピソードを取捨選択しながら、構成をなるべくシンプルにしていきました。

僕が子供の時に映画館で観た
作品の体験や記憶を
今度はお客さんに持ち帰って欲しい
――アオヤマ君の声を演じた北香那さんを起用した理由を教えて下さい。
石田:声優さんや子役など色んな選択肢がありましたが、頭脳明晰な少年ではあるけれど「いざ行動して喋ってみるとやっぱり子供だ!」というツッコミが生じるようなウブさが欲しかったんですね。そういう意味で若手のフレッシュな女優さんがいいのではと考えました。そこでオーディションをしたところ、北さんは僕が求めるそれらの要素プラス“真っ直ぐな少年像”を体現できていた。アオヤマ君の“変さ”というのは、ひねくれている“変”ではなくて、ただただ真っ直ぐなだけなんです。真っ直ぐ突き進んでゆく到達点が同級生より先を行っているから、その差分だけ同級生には“変”に見える。その真っ直ぐさを表現した北さんの演技や声質が良かったです。

――お姉さんの声を演じた蒼井優さんはどうですか?
石田:お姉さん像に対しても色んな意見がありました。例えば、高原で白いワンピースと麦わら帽子を被りながら、透き通る声で笑ってるようなキャラのイメージだったり、逆に『四畳半』に出てくる羽貫さんのような、若干ヤンキー寄りのイメージだったり。はたまたボブカットのサブカルなイメージだったり。なにせ役名が“お姉さん”ですから(笑)象徴的な扱いなんですね。だから、人それぞれの“憧れ”によって姿形が変わるところがあるんです。蒼井優さんの声には“生(なま)感”があるというか、存在感が感じられる。例えば、自分を可愛がってくれる近所のお姉さんのような身近さが欲しかった。蒼井さんの声はちょっと低めでハスキーで飾らない感じがあり、その自然体な感じが“生感”に繋がって、謎のお姉さんの存在感を確かなものにしてくれたし、そしてあとは単純に自分の中で一女性の声としてツボってしまったんです(笑)


――石田監督は『フミコの告白』や『陽なたのアオシグレ』といった過去作でも高低差を利用した上下運動を描いています。作品の中で地理的な高低差を描くことでどのような効果が生まれるのでしょうか?
石田:高低差があると何かとドラマが生まれそうな気がしています。様々な使い方をしていますが、まず給水塔をてっぺんにして丘の上に広がるのはアオヤマ君が住む新興住宅地。丘の下には古い町が広がっているという区分にしています。作中に出てくる「プロジェクト・アマゾン」を追っていくと分かると思いますが、この対比でアオヤマ君が住む丘の上の街のきらびやかさを強調していますし、アオヤマ君が目にする世界の美しさやコントラストにも貢献したく。
――一方で、ポスターのデザインにもなっているペンギンの大群が押し寄せる場面。『陽なたのアオシグレ』の中でも、たくさんの鳥たちが駆け抜けてゆくという描写がありました。
石田:作画泣かせですよね(笑)。原作を読んで最初に描いたイメージボードの中に走るアイデアはなかったんです。でも映画には何かが必要だと思い至り、それならペンギンが歩いているだけではなく、走ったり、飛んだり、あるいは、街並がヘンテコなことになるだとか、先ほど話した上下の高低差を全方位に活かした空間的な遊びが思い浮かんだんです。それは僕が子供の時に映画館で観た作品の体験や記憶が結局は基になっていて、そういう体験を今度はお客さんに持ち帰って欲しいなという想いはありました。ポスターにも描かれているその僕たちがペンギンパレードと呼んでいるお祭り場面は、自分が映画でワクワクする光景、映画というのはそういうものを観るために行くものだと思うんです。

インタビュー・構成:松崎健夫(映画評論家)